「何度言っても、何度言っても片付けてくれない…!」「リビングがいつの間にかおもちゃで埋め尽くされている…」。
そんな光景を見て、ため息をついていませんか? 子供に「片付けなさい!」と言うたびに、お互い嫌な気持ちになってしまう。でも、一体どうすれば子供が自ら進んで片付けてくれるようになるのか、その方法が分からずに困っている方は多いはずです。
実は、子供が片付けないのは「やる気がない」からだけではありません。そこには、大人が気づきにくい理由や、子供の成長段階に合わせた片付けの「仕組み」が関係しているのです。
この記事では、片付けのストレスから解放され、親子ともに笑顔になれる解決策をたっぷりご紹介します。
- なぜ子供は片付けが苦手なのか? その本当の理由がわかります。
- 子供が迷わず片付けられるようになる「魔法の収納ルール」を具体的に解説します。
- 「片付けなさい!」以外の、子供のやる気を引き出す「魔法の声かけ」が身につきます。
もう、イライラしながら片付けを促す必要はありません。今日から実践できる簡単な工夫で、子供が「片付けって楽しい!」と感じるような環境を一緒に作っていきましょう。

スマホで簡単に家事代行を依頼できるサービス。1時間2,790円(税込)〜という手頃な料金設定と、当日3時間前まで予約・変更可能な手軽さが魅力です。独自の研修をクリアしたキャストによる高品質なサービスで、忙しい毎日をサポートします。

1回2,200円(税込)〜という業界最安値水準の料金が最大の魅力。掃除範囲を限定したシンプルなプランで、一人暮らしや特定の場所だけを綺麗にしたい方におすすめです。鍵管理にはGPS端末を装着し、不在時でも安心して利用できます。

業界初の『担当変更し放題サービス』が特徴の家事代行サービスです。相性ぴったりの担当者が見つかるまで無料で何度でも変更できます。スポット利用や定期利用、水回り特化のプランなど、ニーズに合わせた柔軟なプランが用意されています。
なぜ子供は片付けが苦手なの?背景にある理由を理解しよう
子供に「片付けなさい」と何度言っても響かないのは、彼らが意地悪をしているわけでも、わがままなわけでもありません。実は、子供にとっての片付けは、大人とはまったく違う意味を持っているからです。
この根本的な違いを理解するだけで、イライラが減り、子供への接し方が変わるはずです。まずは、子供が片付けをしたがらない心理的な理由を深く掘り下げてみましょう。
子供が片付けない3つの主な理由
「うちの子、どうして片付けてくれないんだろう?」と悩む前に、まずは子供の視点に立って考えてみることが大切です。そこには、以下の3つの理由が隠されています。
- 理由1:片付け方がわからない
大人にとっては当たり前の「片付け」という行為も、子供にとっては高度な作業です。特に、漠然と「お片付けしてね」と言われても、「どこに何を戻せばいいのか?」「どのくらいやれば終わりなのか?」が分からず、途方に暮れてしまいます。片付ける場所が決まっていない、収納方法が複雑など、「どうすればいいか」が不明確な環境だと、子供は行動に移せません。 - 理由2:他のことに興味がある
子供の脳は、新しい刺激や「楽しいこと」に集中するようにできています。遊びに夢中になっている最中に「片付けなさい」と言われると、楽しかった時間が abruptly 終わってしまう感覚に陥ります。この「楽しいことからの強制終了」は、子供にとって非常にストレスフルな出来事なのです。 - 理由3:まだ脳の発達が未熟
片付けには、「今ある状況を把握する」「ゴールを想像する」「手順を考える」「行動に移す」という一連の複雑な思考プロセスが必要です。これらを司る前頭葉は、小学校高学年以降に本格的に発達するため、それまでの子供たちにとって片付けは、大人以上に難しいタスクなのです。
片付けは「遊びの終わり」。だから嫌がる
特に重要なのは、子供にとって片付けは「遊びの終わりを告げる儀式」だということです。大人が「きれいな部屋」という結果を求めるのに対し、子供は「遊びたい」という気持ちが最優先。遊ぶことによって、想像力や思考力を存分に働かせている最中です。
例えば、ブロックで大きな城を築いているとき、それは子供にとって最高の冒険の途中です。そこに「お片付けの時間だよ」と声をかけられると、冒険を強制的に終わらされる感覚になります。片付けが「大人が決めた終わりの時間」だと認識しているうちは、自ら進んで片付けるモチベーションは生まれません。
この背景を理解すると、「なぜ何度言っても片付けてくれないの?」という疑問が「どうすれば片付けを遊びの延長にできるだろう?」という前向きな思考に変わります。次の章では、この理解を元にした具体的な「魔法の収納ルール」をご紹介します。
子供が自分で片付けるようになる魔法の収納ルール3選
子供が片付けない理由が分かったところで、次は具体的な対策に移りましょう。結論から言うと、「子供が自分で片付けたくなるような仕組み」を家庭内に作ることが最も重要です。大人主導の片付けから、子供が主体的に動ける仕組みへと移行するための「魔法の3つのルール」をご紹介します。
ルール1: 「定位置」を決めて住所を教える
子供が片付けを「難しい」と感じる最大の理由は、どこに何をしまえばいいのか分からないからです。これは、大人に置き換えると、会社の書類がどこに保管されているか分からず、ただ漠然と「整理整頓してね」と言われるようなもの。途方に暮れてしまいますよね。
そこで大切なのが、おもちゃ一つひとつに「定位置」、つまり「住所」を決めてあげることです。ポイントは、子供の目線に合わせた「わかりやすさ」。
- 具体的なモノの指定:「ブロックはここに」「ぬいぐるみはここに」と具体的に教える。
- カテゴリー分け:「車のおもちゃ」「ごっこ遊びセット」など、ざっくりとしたカテゴリーで分ける。
さらに効果的なのが、定位置にテプラや手書きのラベルを貼ること。まだ字が読めない子供には、写真やイラストのラベルがおすすめです。「絵と現物が一致している」ことで、子供は迷うことなく片付けられるようになります。例えば、ブロックの入った箱にはブロックの写真を貼る、などですね。
まずは親が一緒に「ここはブロックのおうちだよ」と声をかけながら、モノを元の場所に戻す習慣をつけましょう。住所を覚えることで、子供は「どうすればいいか分からない」というストレスから解放され、自信を持って片付けに取り組めるようになります。
ルール2: 「見える化」で迷わせない工夫をする
片付けのハードルを下げるには、「何が、どこに、どれだけあるか」を子供の目で見えるようにすることが有効です。透明な収納ケースや、蓋のないバスケットなどを活用しましょう。
例えば、こんな工夫が考えられます。
- 透明なケース:中身が見えることで、「探す」という手間が省け、遊びたいおもちゃをすぐに見つけられます。遊んだ後も、どこに戻せばいいか一目で分かります。
- オープンラック:扉のない棚は、子供が自分で出し入れしやすく、片付けへの抵抗感が減ります。ただし、中身がごちゃごちゃになりがちなので、ルール1の定位置をしっかり決めておくことが重要です。
見える化は、子供が片付けをスムーズに行うためのガイドラインになります。逆に、中身の見えない引き出しや、複雑な仕組みの収納は、子供にとっては迷路のようなもの。片付けを面倒に感じさせてしまいます。
ルール3: 「簡単に」戻せる仕組みを優先する
子供の集中力は長く続きません。片付けに時間や手間がかかると、途中で飽きてしまい、「もうやーめた!」となってしまいます。そこで重要なのが、「片付けのプロセスをいかに簡単にするか」です。
- ぽいぽい収納:ボックスやバスケットに「ぽいぽい」と入れるだけの簡単な仕組みは、小さな子供でもすぐにできます。種類別に細かく分けすぎず、まずはざっくりと収納する習慣をつけましょう。
- 子供の背丈に合わせた収納:子供が自分で届く高さに収納スペースを設けましょう。踏み台が必要な場所では、片付けのハードルが上がってしまいます。
- キャスター付きの収納:おもちゃ箱にキャスターをつければ、遊びたい場所に簡単に移動させることができます。片付けの際は、元の場所まで戻すだけなので、持ち運ぶ手間が省けて楽になります。
この3つのルールを実践することで、子供は「どうすればいいか分からない」「めんどくさい」という気持ちから解放されます。次のステップは、子供が自ら「やりたい!」と感じるような、魔法の声かけ術です。次の章で詳しくご紹介します。
「片付けなさい!」は逆効果?やる気を引き出す声かけのコツ
収納の仕組みを整えることは、子供が片付けやすくなるための土台作りです。しかし、それだけでは十分ではありません。子供の「片付けたい!」という意欲を引き出すには、親の声かけが最も重要なカギを握ります。
ここでは、つい言ってしまいがちなNGワードとその理由、そして子供が自ら動きたくなるような魔法の声かけテクニックをご紹介します。
NGワード:「〜しなさい!」は絶対ダメ
片付けない子供を前にすると、つい反射的に「片付けなさい!」「早くしなさい!」と言ってしまいますよね。しかし、この「〜しなさい」という命令形は、子供の自主性を奪い、片付けを「やらされること」と認識させてしまいます。結果的に、子供は片付けを嫌なものだと感じ、さらに抵抗するようになるという悪循環に陥ってしまうのです。
他にも、以下のような言葉もNGです。
- 「どうして片付けないの?」:問い詰められることで、子供は「怒られている」と感じ、自己肯定感が下がってしまいます。
- 「ママは疲れたの!」:親の気持ちを押し付けることで、子供は罪悪感を抱き、片付けに対してネガティブな感情を持ってしまいます。
- 「片付けないとご飯なしだよ」:脅しやご褒美で釣る方法は、一時的な効果はあっても、根本的な片付けの習慣にはつながりません。
大切なのは、命令するのではなく、子供の気持ちに寄り添いながら、片付けをポジティブな行為として捉えさせることです。次に紹介する「魔法の声かけ」をぜひ試してみてください。
魔法の声かけ:「一緒にやろう」の力
「〜しなさい」という命令形から、「〜しようね」という誘いかけに変えるだけで、子供の片付けに対する見方は大きく変わります。中でも特に効果的なのが「一緒にやろう」です。
片付けが苦手な子供にとって、目の前に散らかったおもちゃの山は、途方もない作業に見えます。「一緒にやろう」と声をかけることで、親が味方であることを伝え、「一人でやらなくていいんだ」と安心感を与えられます。具体的には、以下のように声かけを工夫してみましょう。
- 遊びの一環にする:「このおもちゃ、お家に帰してあげようか!」と、擬人化して遊びのように誘う。
- 時間を区切る:「〇〇くんと競争だ!どちらが早く片付けられるかな?」とゲーム感覚を取り入れる。
- できたことを褒める:「わあ、ブロックのおうちができたね!すごい!」と、小さな成功体験を積み重ねさせる。
最初は親が主導で片付けを行い、徐々に子供の担当部分を増やしていくのがポイントです。たとえ少ししかできなくても、「できたこと」を具体的に褒めることで、子供は「片付けは楽しいこと」や「片付けたら褒められる」というポジティブな経験を重ねていきます。
収納の仕組みと声かけのコツを組み合わせることで、子供は「片付けは自分でできること」だと自信を持つようになります。この小さな成功体験が、やがて自立心へとつながっていくのです。最後に、子供の片付けに関するよくある質問をまとめましたので、参考にしてください。
よくある質問(FAQ)
子供が片付けないのはなぜですか?
子供が片付けない主な理由は、片付け方が分からない、遊びに夢中になっている、そして脳の発達が未熟なためです。特に、片付けは「遊びの終わり」を意味するため、子供にとっては抵抗を感じやすい行為といえます。この背景を理解し、親が適切なサポートをすることが重要です。
子供が片付けるようになるにはどうしたらいいですか?
まず、子供が片付けやすい環境を整えることが大切です。「定位置を決める」「見える化する」「簡単に戻せる仕組みを作る」の3つの収納ルールを実践してみましょう。それに加えて、「〜しなさい」という命令形ではなく、「一緒にやろう」と誘うなど、声かけを工夫することで、子供の自主性を引き出すことができます。
子供のおもちゃ収納のコツは?
子供が自分で片付けられるように、収納の仕組みをシンプルにすることがコツです。中身が見える透明なケースや、蓋のないバスケットなどを活用し、おもちゃの住所を明確にしてあげましょう。また、小さな子供には「ぽいぽい」と入れるだけの簡単な収納から始めるのがおすすめです。
子供の片付けはいつから教えるべきですか?
一般的に、1歳半頃から「ものを元の場所に戻す」という習慣を少しずつ教え始めるのが良いとされています。この時期は、大人の真似をしたがる「模倣期」なので、親が楽しそうに片付けている姿を見せるだけでも効果的です。大切なのは、完璧を求めず、焦らず、根気よく続けることです。
まとめ
子供の片付けは、単なる「おもちゃをしまうこと」以上の意味を持ちます。それは、親子の信頼を築き、子供の自立心を育む大切なステップです。この記事でご紹介したポイントを振り返り、実践する第一歩を踏み出しましょう。
- 片付けない理由を理解する:子供が片付けをしないのは、方法が分からなかったり、遊びに夢中だったりするから。感情的に怒らず、その理由に寄り添うことが大切です。
- 3つの魔法のルール:「定位置」「見える化」「簡単さ」を意識した収納の仕組みを作りましょう。
- 声かけを工夫する:「〜しなさい」ではなく、「一緒にやろう」というポジティブな言葉で、子供のやる気を引き出しましょう。
完璧な片付けを求めるのではなく、まずは「できた!」という小さな成功体験を積み重ねることが、子供の自信につながります。今日からできる小さな一歩を、ぜひ親子で一緒に始めてみませんか?
片付けのストレスから解放され、親子の笑顔があふれる毎日を手に入れましょう!
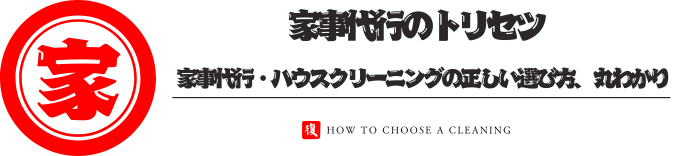




コメント